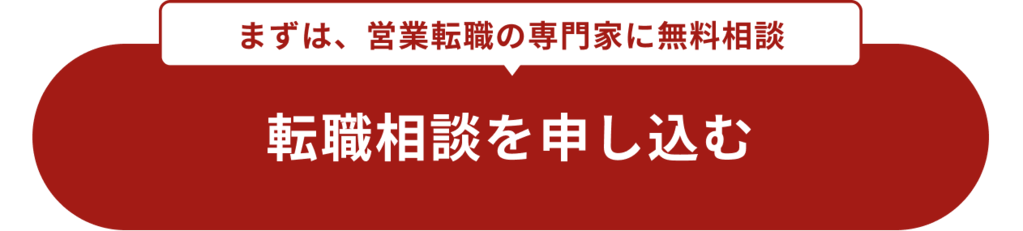退職から入社までの準備・手続きを完全ガイド|流れ・必要書類・スケジュール例も解説
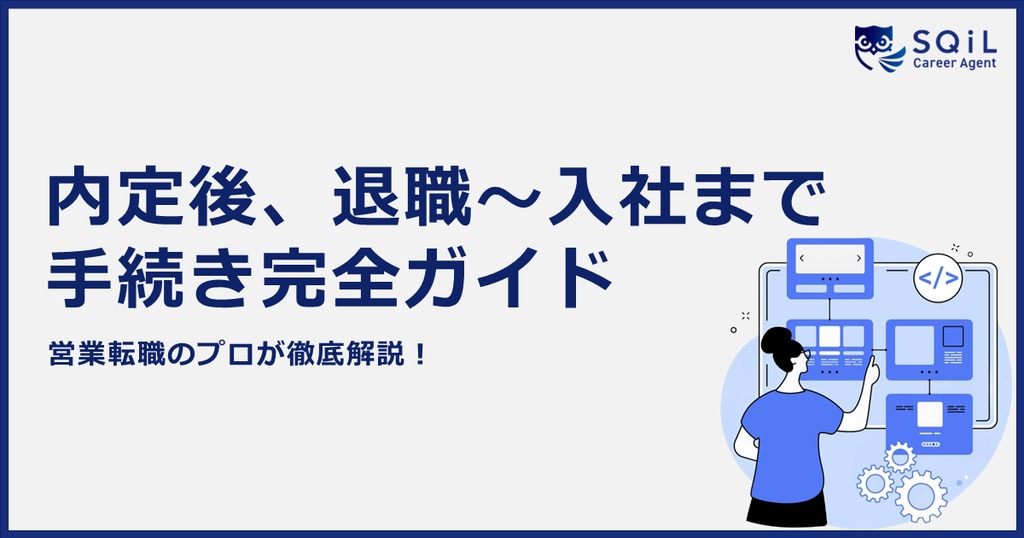
転職が決まって安心したのも束の間、「退職の手続きって何から始めればいい?」「入社準備はいつまでに何をすべき?」と不安を抱える人も多いのではないでしょうか。
転職では現職の退職手続きと転職先の入社準備を並行して進める必要があり、思った以上にやることが多く戸惑う人も少なくありません。特に初めての転職の場合は、慣れない手続きややるべきことの多さに気持ちが焦ってしまうこともあるでしょう。
本記事では、退職から入社までに必要な手続きや書類、準備の流れを時系列でわかりやすく解説します。退職・入社準備の最終チェックリストも紹介するので、「何から始めるべきか分からない」という不安を抱える人はぜひ確認してみてくださいね。
目次[非表示]
- 1.退職から入社までのスケジュールと準備の全体像
- 1.1.退職・入社のスケジュール例
- 1.2.退職・入社準備を並行して進める必要がある理由
- 2.【STEP1】内定後にやるべき退職・入社準備
- 2.1.内定条件の確認と質問すべきポイント
- 2.2.内定承諾・辞退の正しい連絡方法
- 2.3.入社日・退職日の調整の仕方
- 3.【STEP2】現職での退職交渉と準備
- 3.1.上司への退職意思の伝え方とタイミング
- 3.2.退職届・退職願の正しい書き方と提出の流れ
- 3.3.引継ぎ準備と引継ぎ資料の作り方・注意点
- 3.4.挨拶回りで信頼を残すポイント
- 4.【STEP3】退職時に必要な手続きと返却・受取物
- 4.1.会社へ返却すべきもの
- 4.2.会社から受け取る書類
- 5.【STEP4】入社準備に必要な手続き・書類・持ち物
- 5.1.入社時に提出する必要書類一覧
- 5.2.転職先から渡され記入・提出する書類
- 5.3.必要に応じて求められる追加書類
- 5.4.入社初日の持ち物と心構え
- 6.退職から入社までブランク期間がある場合の手続き
- 6.1.健康保険の切替手続きの流れ
- 6.2.雇用保険の失業給付申請方法
- 6.3.年金手続き
- 6.4.税金関連の手続き
- 7.退職・入社準備をスムーズに進めるポイント
- 8.退職・入社準備の最終チェックリスト
- 8.1.退職時の返却・受取物チェックリスト
- 8.2.入社準備・持ち物チェックリスト
- 9.まとめ
退職から入社までのスケジュールと準備の全体像

転職活動が終わり内定が出たら、次は「退職」と「入社準備」のフェーズに入ります。
この期間は、現職への退職交渉や引継ぎ、新しい職場に向けた手続きなど、同時並行でやるべきことが多く発生します。特に退職日と入社日の間にブランクがある場合には、保険や年金、税金の手続きも必要になるため、全体スケジュールを把握しておくことが非常に重要です。
さらに、精神的にも身体的にも負担がかかりやすい時期なので、計画的に進めることがストレス軽減につながります。
それでは、退職から入社までのスケジュールと準備の全体像を見ていきましょう。
退職・入社のスケジュール例
一般的には、内定を得てから1〜2ヶ月以内に退職・入社するケースが多く、以下のようなスケジュールが想定されます。
スケジュール例
・内定獲得:4月1日
・内定承諾・退職交渉:4月上旬
・退職日:5月末
・入社日:6月1日
この間に、退職願の提出、業務引継ぎ、書類の返却・受け取り、入社に向けた必要書類の準備などを並行して進める必要があります。これらのタスクを同時に行うことで、時間的余裕を確保しつつトラブルを回避しやすくなります。
スムーズな転職のためには、日付を逆算して余裕をもったスケジュール管理がカギとなります。余裕がないと急な体調不良や書類不備などが起こりやすいため、できるだけ早めに準備を始めることをおすすめします。
退職・入社準備を並行して進める必要がある理由
退職準備と入社準備を同時に進める最大の理由は、社会保険・税金の空白リスク低減のためです。
退職日と入社日の間に空白期間ができると、健康保険や年金の切替手続き、住民税や所得税の支払いが個人で必要になることがあります。加えて、ブランク期間中の生活費や保険料の負担も考慮しなければならず、これらのリスクを回避するためにも両者をスムーズに繋げることが望ましいといえます。
なお、退職理由が会社都合退職と自己都合退職で失業給付の給付条件や給付期間が異なりますので、自分がどちらなのかは明確にしておくことが大切です。
ブランクを避けたい場合は、入社日と退職日が連続するよう早めに調整し、手続き漏れがないよう両者を計画的に進めることが重要です。転職先や現職の担当者と密に連絡を取り合い、柔軟に対応できるようにしておきましょう。
【STEP1】内定後にやるべき退職・入社準備

内定が出たらとにかく喜びたいところですが、入社前には確認すべきことや準備すべきことが多数あります。転職活動の最後の段階として、ここでの対応がその後の働き始めに大きな影響を与えるため、慎重かつ丁寧に進めることが大切です。
入社後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、無用なトラブルやストレスを避けるためにも、労働条件や入社スケジュールをしっかり確認し、現職との退職日調整も並行して進めましょう。
ここでは、内定後に最初に取り組むべき重要なステップを解説します。
内定条件の確認と質問すべきポイント
内定通知を受け取ったら、給与や勤務時間、勤務地、雇用形態、試用期間の有無・条件、入社日などをよく確認しましょう。
不明点があるまま内定を承諾すると、後からトラブルになる可能性があります。特に試用期間中の待遇や評価基準は要確認です。聞きづらい内容であっても、承諾前に確認したほうが、入社後に後悔するリスクを減らせます。
重要な条件面で気になる点については、採用担当者に遠慮なく質問し、不安や誤解を残さないようにしましょう。
内定承諾・辞退の正しい連絡方法
内定を承諾または辞退する際は、まず電話で担当者に連絡し、その後に正式なメールを送るのが基本です。
電話では簡潔に意思を伝え、メールで証跡を残す形にしましょう。

💡 エージェントを利用している場合は?
企業担当者に直接連絡する必要はありません。エージェント経由で内定承諾や辞退の意思を伝えれば、企業への連絡も代行してくれるため、担当エージェントに迅速かつ正確に連絡することが最優先です。
辞退の場合も、感謝の気持ちと辞退理由を簡潔に伝えることで、印象を損なわずに済みます。承諾する場合は、企業が指定した書類や締切日にも注意し、スムーズな対応を心がけましょう。
【内定承諾メールの例】
件名:内定承諾のご連絡(氏名) お世話になっております。 本日は、内定のお知らせをいただき誠にありがとうございました。 入社に向けて、提出書類や手続き等につきましても、誠意をもって対応させていただきます。 ――― |
【内定辞退メールの例】
件名:内定辞退のご連絡(氏名 〇〇株式会社 お世話になっております。 誠に恐縮ではございますが、熟慮の結果、今回は貴社の内定を辞退させていただくことにいたしました。 貴重なお時間を割いて選考・面接の機会をいただいたにもかかわらず、このような結果となりましたこと、深くお詫び申し上げます 貴社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。 ――― |
入社日・退職日の調整の仕方
入社日と退職日の調整は、現職の業務引継ぎと新しい職場の都合を両立させるための重要な作業です。
入社日がすでに決まっている場合は、それに合わせて退職日を逆算します。
ブランクを避けたいなら、退職日翌日が入社日になるよう調整すると社会保険や税金の手続きもスムーズです。転職先にも状況を説明し、柔軟に相談しましょう。
【STEP2】現職での退職交渉と準備

転職を決めた後は、現職での円満な退職に向けた対応が欠かせません。
引継ぎや関係各所への挨拶など、最後まで誠実に対応することで、これまで築いた信頼関係を保ったまま退職できます。ここでは、退職の意思表示から手続き、最終出社日までにやるべきことを順を追って解説します。
上司への退職意思の伝え方とタイミング
退職の意思は、まず直属の上司に対して、できるだけ早めに伝えましょう。法律上は、正社員でも原則として「退職希望日の14日前まで」に申し出れば退職は可能とされています(民法第627条)。
ただし、引継ぎや人員調整、職場への配慮を考慮すると、1〜2ヶ月前を目安に伝えるのが一般的なマナーです。
突然の話ではなく、落ち着いた場で「相談がある」と時間を取り、感謝の気持ちを伝えたうえで退職の意思を説明しましょう。会社の規定に従い、正式な申し出のタイミングも意識することが重要です。
退職届・退職願の正しい書き方と提出の流れ
退職の意思を伝えた後は、会社の規定に沿って「退職届」または「退職願」を提出します。
一般的に「退職願」は撤回が可能な意思表示(会社に退職を「お願い」し、会社側が「承諾」する)であり、「退職届」は確定的な申し出として法的拘束力があります。
提出の際は、会社のフォーマットや指定書式がある場合はそれに従いましょう。ない場合は、以下のような基本的な構成を押さえて作成してください。
- 冒頭に「退職願」または「退職届」のタイトル
- 所属部署・氏名
- 退職の理由(「一身上の都合により」が一般的)
- 退職希望日
- 提出日・宛名(例:○○株式会社 代表取締役 ○○様)
手書きが指定されている場合は黒のボールペンまたは万年筆で丁寧に記入し、誤字脱字には注意を。
提出は原則として直属の上司に手渡しで行いましょう。退職希望日から逆算し、最低でも2〜3週間前には提出できるよう準備しておくとスムーズです。
引継ぎ準備と引継ぎ資料の作り方・注意点
引継ぎは、職場に迷惑をかけないためだけでなく、自身の信頼を保つうえでも重要なポイントです。
業務ごとの担当者、進行状況、注意点などを整理し、口頭ではなく資料として残すようにしましょう。業務マニュアルやチェックリストを作成すると、後任者が理解しやすくなります。
個人のノウハウもなるべく文書化し、余裕をもって引継ぎ日程を調整しましょう。また、転職を決意した段階で引継ぎ資料の準備を進めておくと、退職交渉の際にも「すでに引継ぎ準備ができている」と示せるため、円満退職につながりやすくなります。
挨拶回りで信頼を残すポイント
最終出社日が近づいたら、関係部署やお世話になった同僚・上司への挨拶回りを行いましょう。
対面が難しい場合はメールでもOKですが、できるだけ直接感謝の気持ちを伝えるのが理想です。業務面だけでなく人間関係も円満に終えることで、退職後も良好な関係が続くことがあります。
転職後に取引先として再会する可能性もあるため、印象よく締めくくることが大切です。
以下は、挨拶メールの一例です。
件名:退職のご挨拶(○○部・氏名) |
このように、感謝の気持ちを具体的に伝えることで、相手に誠意が伝わりやすくなります。
【STEP3】退職時に必要な手続きと返却・受取物

退職時には、これまでの勤務先から貸与・支給されていた物の返却や、公的手続きに必要な書類の受け取りが発生します。
これらの対応を確実に行わないと、入社先での手続きに支障が出たり、あとでトラブルになる可能性もあります。スムーズに次のステップへ進むためにも、退職日に向けて必要な確認と準備をしておきましょう。
会社へ返却すべきもの
退職時には、会社からの支給品をすべて返却する必要があります。たとえば社員証やセキュリティカードなどの身分証明書類、取引先に渡していた名刺の残り、通勤定期券、健康保険証などが該当します。
さらに、業務で使用していたパソコンやスマホ、制服、書類、USBメモリなどのデータ類も対象です。私物と混ざらないよう、事前に整理しておくと安心です。
特に注意したいのが、顧客情報や名刺の取り扱いです。
退職後に持ち出したことが発覚し、情報漏洩や不正使用とみなされてトラブルに発展するケースもあります。不要な誤解や問題を避けるためにも、「会社に属するものはすべて返却する」という意識を持ち、慎重に整理しましょう。
以下のチェックリストを参考に、漏れがないよう準備を進めましょう。
□ 身分証関連
- 社員証
- 入館証/セキュリティカード
- 名刺(未使用分)
□ 金銭・通勤関連
- 通勤定期券(会社支給の場合)
- 経費精算関連のレシート・伝票など
□ 保険・福利厚生関連
- 健康保険証
- 福利厚生に関する書類・貸与物
□ IT・備品関連
- ノートPC・社用スマートフォン
- USBメモリ・外付けハードディスク
- 業務マニュアル・書類
- 貸与された文房具や備品(電卓・印鑑など)
□ 制服・その他
- 制服・作業着・名札など
- 社章・ピンバッジ
会社から受け取る書類
退職後の転職先での手続きや、公的申請のために必要な書類は以下の通りです。忘れずに受け取りましょう。
✅ 転職先が決まっている場合に必要な書類
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 源泉徴収票
✅ 転職先が未定の場合に追加で必要な書類
- 離職票(失業給付の申請に必要)
- 被保険者資格喪失証明書(健康保険切替時に必要)
発行に数日かかることもあるため、早めに依頼しておくことが大切です。
【STEP4】入社準備に必要な手続き・書類・持ち物

退職手続きが一段落したら、次は新たな職場での入社準備です。入社日当日までに必要な書類を揃え、提出漏れがないよう注意しましょう。
あわせて初日の持ち物や心構えも確認しておくと、不安なく新生活をスタートできます。ここでは、入社前に準備すべき書類や持ち物を整理して紹介します。
入社時に提出する必要書類一覧
新しい勤務先での入社手続きには、以下の書類の提出が求められます。漏れのないよう、事前に準備しておきましょう。
✅ 入社時に必要な主な書類
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
┗年金記録の確認に使用 - 雇用保険被保険者証
┗雇用保険の継続手続きに必要 - 源泉徴収票(前職分)
┗年末調整のために必要
※会社によっては住民票やマイナンバーの提出を求められることもあるため、事前に案内をよく確認しておくことが大切です。
入社当日や指定日までに、必ず準備しておきましょう。
転職先から渡され記入・提出する書類
入社にあたっては、新しい勤務先からもいくつかの書類を渡され、記入・提出が求められます。漏れなく準備・提出しましょう。
✅ 入社時に記入・提出が必要な書類
- 扶養控除等(異動)申告書
┗所得税の計算に使用される基本書類 - 健康保険被扶養者異動届
┗家族を健康保険の扶養に入れる場合に必要 - 給与振込口座届出書
┗給与の振込口座を登録するための書類 - 通勤交通費申請書(※必要な場合)
┗定期代など通勤費の申請に使用
※企業によっては、誓約書や身元保証書などの提出も求められる場合があります。
書類の提出期限は厳守し、早めに記入・準備することを心がけましょう。
必要に応じて求められる追加書類
職種や企業によっては、いくつかの追加書類の提出が求められることがあります。案内があった際には、早めに準備しておきましょう。
✅ 追加で提出を求められることがある書類
- 健康診断書
┗入社前の健康状態を確認するために提出を求められることがある - 入社誓約書・入社承諾書
┗会社の規定や方針に同意する旨を記した書類 - 身元保証書
┗社員の身元を保証する第三者の署名が必要な書類 - 住民票記載事項証明書
┗住所確認や身元確認のために必要となることがある - 卒業証明書・資格証明書
┗最終学歴や保有資格の証明として必要な場合がある
※提出を求められる書類は企業ごとに異なります。入社案内の指示に従って、漏れなく準備しましょう。
入社初日の持ち物と心構え
入社初日は、緊張しやすい一方で職場の第一印象が決まる大切な日です。忘れ物をせず、好印象を与えられるよう準備しましょう。
✅ 持ち物リスト
- 筆記用具(ボールペン・シャープペン・消しゴムなど)
- メモ帳
- 印鑑
- 提出書類一式(事前に案内があったもの)
- 社員証用の証明写真(必要な場合)
- 身分証明書(本人確認が必要な場合)
✅ 服装とマナーの心構え
- 清潔感のある服装を選ぶ(スーツやオフィスカジュアルなど企業に合わせて)
- 明るい挨拶を心がける
- 指示を素直に聞く姿勢を大切に
- わからないことは遠慮せず質問する
わからないことは遠慮せず確認し、好印象のスタートを目指しましょう。
退職から入社までブランク期間がある場合の手続き

退職から入社までに数週間〜数ヶ月のブランクがある場合、公的制度の手続きが必要になります。
健康保険や年金、雇用保険、税金の対応をしっかり行っておかないと、思わぬ出費や不利益につながるかもしれません。ここでは、ブランク期間中に忘れず対応すべき主な公的手続きを確認していきましょう。
健康保険の切替手続きの流れ
退職すると会社の健康保険の資格を失うため、いずれかの方法で切替が必要です。
【選べる健康保険の切替方法】
- 国民健康保険(国保)に加入:市区町村役所で手続き
- 任意継続被保険者制度を利用:退職前の健康保険を最長2年間継続(申請は退職後20日以内)
- 家族の扶養に入る:配偶者などの健康保険に加入(収入などの条件あり)
任意継続を希望する場合は、手続き期限に注意が必要です。健康保険組合によって条件が異なることもあるため、必ず詳細を確認しましょう。
雇用保険の失業給付申請方法
転職先が未定で雇用保険に一定期間以上加入していた方は、ハローワークで失業給付(基本手当)の申請が可能です。※再就職の意思と能力があり、積極的に就職活動を行っていることが条件となります。
✅ 主な必要書類
- 離職票(1と2)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 写真(縦3cm×横2.5cm程度を2枚)
- 印鑑(認印で可)
- 普通預金の通帳またはキャッシュカード(本人名義)
申請後は7日間の待期期間があり、その後に自己都合退職などの場合は1ヶ月の給付制限期間(※2025年4月以降に短縮)を経て、支給が開始されます。
支給までに1〜2ヶ月程度かかる場合があるため、早めに手続きを進めましょう。
年金手続き
退職すると厚生年金(第2号被保険者)の資格を失うため、ブランク期間中は「国民年金第1号被保険者」としての切替手続きが必要です。
市区町村の役所にて、退職後14日以内を目安に手続きを行いましょう。もし保険料の支払いが難しい場合は、以下の制度の活用も検討できます。
- 免除制度:所得が一定以下の人向けに、保険料の全額または一部が免除される制度
- 納付猶予制度:50歳未満が対象で、保険料の支払いを一時的
どちらも申請が必要なので、忘れずに役所で確認しましょう。
税金関連の手続き
ブランク期間中は、住民税や所得税の納付にも注意が必要です。住民税は前年の所得に基づいて課税され、退職後も支払い義務があります。
会社の給与天引きがなくなるため、納付書での個人払いとなります。また、年末調整を受けられない場合は、翌年2月〜3月に確定申告を行い、過不足を精算しなければなりません。
納期限を逃さず、早めの確認を行いましょう。
退職・入社準備をスムーズに進めるポイント

退職と入社の準備はやることが多く、想像以上に時間と労力がかかります。スムーズに進めるためには、段取りよく進める工夫が欠かせません。
書類や手続きの漏れを防ぎ、余裕を持って新しい職場でのスタートを切るために、以下の3つのポイントを意識して準備を進めましょう。
返却・提出書類は漏れがないかチェックする
退職時・入社時の双方で、多くの書類のやり取りが発生します。
会社へ返却すべき物(健康保険証、社員証など)や、入社時に提出すべき書類(源泉徴収票、年金手帳など)に漏れがあると、後々トラブルになるかもしれません。
事前にリストを作り、返却・提出のチェックを忘れず行うことで、安心して手続きを進められるでしょう。
必要書類・手続きは事前確認し余裕を持って準備する
退職・入社に関する手続きの中には、期限があるものや発行まで時間がかかる書類もあります。
たとえば、源泉徴収票や離職票は退職後すぐに受け取れない場合もあるため、早めに確認・依頼しておくことが重要です。
提出日が迫って慌てないよう、必要なものは早めにピックアップし、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
スケジュール管理は表・リスト化で見える化する
退職・入社に関する手続きやタスクは、時期ごとに多岐にわたるため、頭の中だけで管理するのは危険です。
やるべきことをリスト化し、期限付きでスケジュール表にまとめることで、全体像を把握しやすくなり、抜け漏れも防げます。
スマホのカレンダーアプリやチェックリスト機能を活用するのもおすすめです。
退職・入社準備の最終チェックリスト

退職・入社の準備が一通り終わったら、最終確認としてチェックリストで見直しましょう。
提出・返却漏れや手続き忘れがあると、転職後に面倒なトラブルが発生することもあります。
ここでは、退職時と入社時に分けて、それぞれ確認すべきポイントを一覧で整理しました。こちらを参考にしつつ、自分に必要なものを追加・削除して漏れがないように対応しましょう。
退職時の返却・受取物チェックリスト
退職時には会社に返却すべき物と、自分が受け取るべき書類があります。漏れがあると後から連絡や手続きが必要になるため、事前にしっかり確認しましょう。
✅ 返却するもの
- 健康保険証
- 社員証、入館証などの身分証明書
- 名刺・通勤定期券
- 業務用PC、スマホ、USBなどの会社支給品
- 業務書類やデータ類
✅ 受け取るもの
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 源泉徴収票
- 離職票(転職先未定の場合)
- 被保険者資格喪失証明書(転職先未定の場合)
入社準備・持ち物チェックリスト
新しい職場でスムーズに業務に集中するには、必要書類や持ち物をきちんと揃えておくことが大切です。入社初日に慌てないよう、事前に準備しておきましょう。
<提出書類>
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 扶養控除等申告書
- 健康保険被扶養者異動届
- 給与振込口座届出書
<必要に応じて>
- 健康診断書
- 入社誓約書・承諾書
- 身元保証書
- 住民票記載事項証明書
<入社初日の持ち物>
- 印鑑・筆記用具・メモ帳
- 提出書類一式
- 指定があれば写真や本人確認書類など
まとめ
退職から入社までの期間には、手続き・調整・準備と、多くのタスクがありますが、事前に全体の流れを把握しておけば、混乱せずに着実に進められます。
本記事で紹介したスケジュールやチェックリストを活用すれば、必要書類の提出漏れや手続きの抜けを防ぐことが可能です。また、退職・入社に関する不安も軽減され、心の余裕を持って対応できるようになります。転職活動の一環として、こうした「抜け・漏れ防止」も自己管理の重要な一部といえるでしょう。
余裕を持った行動は、周囲からの信頼や印象にもつながります。新しい職場で好スタートを切るためにも、円満な退職・万全な入社準備を心がけたいところです。
これから新しい環境で気持ちよくスタートを切るためにも、準備は早め・丁寧に行い、円満退職・スムーズな入社を実現させましょう。