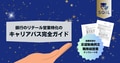「要件定義ではなく、要求定義」を営業に──スマレジが貫くコンサルティング営業の哲学と、採用成功に欠かせないエージェントとの共創|株式会社スマレジ様
 クラウドPOS「スマレジ」を中心に、店舗運営の課題解決を支援するスマレジは、現在中途採用を強化中。2024年の組織改編を機に、採用の最終基準にも変化がありました。
クラウドPOS「スマレジ」を中心に、店舗運営の課題解決を支援するスマレジは、現在中途採用を強化中。2024年の組織改編を機に、採用の最終基準にも変化がありました。
SQiL Career Agentでは、スマレジの採用方針を踏まえ、同社で活躍できる人材をご紹介してきました。紹介理由や候補者の強みを丁寧に整理・言語化することで、求職者だけでなくスマレジの採用活動も支援しています。
今回は、スマレジで採用窓口を務める三次さんと、SQiL Career Agentの武・菅谷が座談会を実施。スマレジの求める人物像や、入社後に描けるキャリアパスについてお話を伺いました。
★Point
- 「要求定義」の思考が根づく、目的起点の組織文化
- 顧客の理想像に伴走するコンサルティング営業スタイル
- 採用精度を高める、エージェントとの対等なパートナーシップ
レジを起点に店舗運営を支えるDXソリューション

━━ スマレジの事業内容を教えてください。
三次さん:私たちはクラウド型POSサービス「スマレジ」を中心に、決済や勤怠管理、在庫管理、売上分析といった、店舗運営に関わるさまざまなサービスを提供しています。社名に「レジ」が入っているのでレジスターの会社という印象を持たれることも多いのですが、実際にはレジを起点として、店舗が抱えるさまざまな課題を解決するソリューションを開発・提供しています。
菅谷:レジのDX化には、どのようなメリットがあるのでしょうか?
三次さん:一番のメリットは、業務効率や経営の質を大きく引き上げられることです。これまで人の手で行っていたオペレーションや事務作業が、デジタル化によって自動化・効率化され、結果として労働生産性が向上します。
さらに、売上や在庫などのデータがリアルタイムで可視化されることで、データドリブンな経営判断や需要予測がしやすくなり、再現性のある運営が可能になります。加えて、ユーザーアプリやECとの連携を通じて、顧客の購買行動の変化にも柔軟に対応できるなど、レジのDXによってお店の可能性は大きく広がります。
こうしたDXのメリットを最大限に活かせるのが、クラウド型のスマレジです。常に最新の状態に保てるうえ、基本料金は月額5千円からと手頃で、小規模店舗でも導入しやすいのが特徴です。
━━ 特に導入が進んでいるのは、どのような業種でしょうか?
三次さん:スマレジユーザーの約40%は小売業の企業です。というのも、スマレジには発注・仕入・在庫の店舗間移動など、小売業に欠かせない機能が多数そろっているからです。
菅谷:レジといえば、飲食店のイメージが強いのですが、モノの出入りを管理する部分に強みがあるのですね。
三次さん:おっしゃる通りです。実際の導入数でいえば、小売店の方が多いですね。アパレル、食品、書店、薬局など、小売といっても業種は多岐にわたります。もちろん、次に多いのが飲食店ですが、そのほかにもクリニックなど、幅広い業態で利用されています。こうした汎用性の高さが、スマレジの特長のひとつです。
━━ スマレジは、主に実店舗での利用が中心ですか?
三次さん:基本は実店舗ですが、近年はEC連携にも注力しています。2024年にはEC運営を一気通貫で支援する「ネットショップ支援室」がグループ入りし、スマレジと連携することで、実店舗とオンライン双方の顧客管理が可能になりました。
菅谷:特に小売店に強みを持つスマレジだからこそ、実店舗とECの両方に価値提供ができるのですね。
「お店を元気に、街を元気に!」を実現する使命と文化

━━ スマレジが目指す世界観を教えてください。
三次さん:私たちが掲げているミッション「お店を元気に、街を元気に!」が、まさにスマレジの目指す世界観そのものです。
私たちのサービスを通じて、一つひとつのお店が自らの運営を「科学」し、データに基づいた経営を行うことで、店舗が元気になる。そんなお店が増えることで、街や社会全体にも活力が広がる循環をつくっていきたいと考えています。
2024年7月の代表交代に伴い、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)も刷新しましたが、これまでの価値観を再定義したもので、大きな方向転換ではありません。たとえばバリューは、「行けるとこまでいく!」「要件定義ではなく、要求定義」「家族に誇れる仕事を」など、より具体的で伝わりやすい表現にアップデート。社員の間でも自然と共感が広がり、Slack上にはスタンプがつくられるなど、自分たちらしさを再確認できた節目になったと感じています。
━━ お店を元気にするうえで、スマレジが果たす役割について詳しくお聞かせください。
三次さん:お店を運営していくうえで、欠かせないのが「データの蓄積」と、それを支える「基幹システム」です。スマレジは、その土台としての役割を担っています。
菅谷:スマレジは提案型の営業スタイルではありますが、店舗にとって必要不可欠なマストハブに近いサービスだと捉えています。
三次さん:そうですね。根本的には業務に欠かせないシステムですが、導入や活用の幅が非常に広いため、提案する立場としてもやりがいのある仕事です。
「要求定義」を軸にしたスマレジの営業の特徴

━━ スマレジの営業職の特徴をお聞かせください。
三次さん:スマレジの営業職は、インサイドセールスとフィールドセールスが連携し、お客様の課題整理からご提案、導入支援までを一貫して担っている点が特徴です。
現状、案件の9割以上がインバウンド型(反響営業)で進み、その対応を担うフィールドセールスの採用も積極的に行っています。 一見すると「インバウンドなら簡単なのでは?」と思われがちですが、実際には難易度が高い場面も多くあります。お問い合わせいただいた時点では、お客様自身が課題を明確に捉えきれていないケースが多く、漠然とした理想像やニーズを、理想像の言語化から始めるケースも少なくありません。
理想の店舗運営はお客様ごとに異なり、正解が一つに決まることはありません。フィールドセールスは、対話を通じて理想像を形にする伴走者としての役割を担っています。そのため、スマレジの営業スタイルはコンサルティング営業に近いと言えるでしょう。
武:バリューにもある「要求定義」という言葉が、まさにぴったりですね。お客様の言葉を表面的に受け取るのではなく、その背景や本質に迫る姿勢が求められますね。
三次さん:「要件定義ではなく、要求定義」は、スマレジが大切にしている考え方のひとつです。
お客様の要望をそのまま形にするのではなく、「なぜそれが必要なのか」という背景に立ち返り、課題の本質を見極めることを重視しています。POSシステムは汎用性が重要なので、個別のご要望すべてに対応してしまうと、かえって使いづらくなってしまうこともあります。そのため、お客様の課題を本質から整理し、本当に価値のある提案をすることが営業にとっても非常に重要です。
この姿勢は営業だけでなくカスタマーサポートにも共通しています。自社内で運営するコールセンターでも、「どうしたらいいか?」という相談に対して、「なぜそうしたいのか?」と背景から確認することで、シンプルな設定変更で解決できるケースもあります。全職種で要求定義の視点を大切にしています。
菅谷:インバウンドリードといえども、単に「How(どうやるか)」を提案するのではなく、「What(何を実現したいか)」を丁寧に紐解く。その意味でも、コンサルティング的なアプローチですね。
━━ コンサルティング営業を行うには、専門性も求められそうですね。
三次さん:たしかに、そう聞くとハードルが高いと感じる方も多いかもしれませんが、スマレジでは段階的にスキルを習得できる環境があります。
まずは、ニーズが明確で提案の幅が限られる案件から経験を積み、慣れてきた段階で、複数店舗を展開する企業の情シス担当者など、より専門性の高いお客様を担当していただきます。この段階では、既存システムとの連携や構成設計を含む提案を行い、営業自らがシステム構成図を作成することもあります。
武:営業の中にもフェーズがあり、徐々に成長していける仕組みなのですね。
三次さん:はい、段階的にステップアップできるのは当社の営業の魅力です。いきなり高度な提案を求められるのではなく、地に足をつけて着実に経験を積みながら、最終的にはIT営業として専門性を発揮できる。長い目でキャリアを考えたい方にこそ、フィットする環境だと思います。
━━ 入社後のキャリアパスについても教えてください。
三次さん:フィールドセールスで入社後は、リーダー職を目指すだけでなく、パートナーセールスやカスタマーセールス、エンタープライズセールス、営業企画など、幅広いキャリアの選択肢があります。
菅谷:とても興味深いですね!上場企業としての土台を持ちつつ、挑戦を楽しめるダイナミックな空気感があるのが魅力的ですね。
三次さん:そうですね。一人ひとりの「やってみたい」を応援できる柔軟なカルチャーも、スマレジらしさの一つです。
多様性と成長意欲を重視した採用方針

━━ スマレジ全体での採用についてお伺いしたいと思います。スマレジは大阪本社に加え福岡、東京、名古屋と4拠点で採用をしていますが、違いはありますか?
三次さん:関西では「大阪発のベンチャー」という点に共感して応募いただく方が多いです。MVVの刷新を通じて、地元への想いに共鳴する方も増え、名古屋や福岡でも順調に採用が進んでいます。
一方で東京では、「お店を元気に、街を元気に!」というミッションが他地域ほどは刺さっていない印象です。入社後に共感してくださることも多いのですが、応募のきっかけとしてはやや弱いかもしれません。
菅谷:その点、どのような発信を意識されていますか?
三次さん:代表とも話す中で、スマレジの営業職は「成長意欲のある方」にマッチするという整理をしました。POSは人事労務や会計のような法律ドリブンではなく、お客様ごとに課題も理想も異なるため、ニーズを言語化して提案する力が求められる。だからこそ、自ら学び成長したい方にこそ合う環境だと考えています。
武:かなり高い難易度ですね。
三次さん:はい。だからこそ、営業として成長したいと考えている方にとっては、チャレンジしがいのある環境です。経験を問わず、コンサルティング営業のスキルを着実に磨けるのは当社ならではの魅力だと思います。「今の職場で営業力が伸びているのか」と感じている方には、次の一歩としてぜひ検討いただきたいですね。
━━ 採用する際に重視している点はありますか?
三次さん:今期から営業職の採用では、入社によって組織全体の水準を引き上げ、新たな価値観や刺激をもたらしてくれるかどうか、という視点を重視しています。
実際に今期ご入社いただく方々は、ラクロス全国優勝経験者や海外生活経験者など、多彩で個性あふれる方ばかりです。
武:それぞれに、何か光るものを持っている方が多いのですね。
━━ 採用基準を変えたきっかけは何だったのでしょうか?
三次さん:組織体制の変化が大きな要因です。これまでPOSやタイムカードなど、サービスごとに分かれていたセールス組織が、営業本部として統合されました。
その中で「クロスセルファースト」という方針が掲げられ、より多様な営業スタイルが求められるようになりました。一人ひとりの個性や強みを活かすためにも、新たな採用方針が必要になったというわけです。
━━ 強みや個性を活かした営業によって、組織の雰囲気も変わりそうですね。
三次さん:今のメンバーも、実は心の中に熱い想いを秘めている人ばかりです。そこにさらに多様なバックグラウンドを持つ方が加わることで、組織としての厚みが増すと感じています。
当社は、2031年にARR(年間経常収益)300億円の達成を目指しています。その実現には、今までのやり方にとらわれず、新しい販路や手法を切り拓いていく必要があります。だからこそ、多様な価値観や経験を持った方々にジョインしていただきたいと考えています。
武:成長の限界を突破していくには、多様な視点が欠かせないということですね。
採用の原動力は「働く姿」とバリュー共感

━━ 三次さんはスマレジの採用を一手に担っていますが、採用担当者としてのやりがいについてお聞かせください。
三次さん:やはり、入社された方がオフィスでイキイキと働いている姿を見ると、大きなやりがいを感じます。
「転職してよかったです」「次はこんなことにチャレンジしてみたいです」といった声を面談で直接聞ける瞬間は、特に嬉しいですね。入社後の面談も私が担当しているので、その変化や前向きな気持ちを間近で感じられることがモチベーションになっています。
武:私も、求職者の方が入社後にイキイキと活躍されている姿を見ると本当にうれしいですし、何より大事にしているポイントです。
━━ 三次さんが特に共感しているバリューがあれば教えてください。
三次さん:私は「要件定義ではなく、要求定義」というバリューに特に共感しています。業務に取り組む際、表面的な指示だけでなく、その背景や本来の目的をしっかり考える文化があるんです。場合によっては、代表から「それって何のためにやるの?」と直接聞かれることもあります。
目的に立ち返ることが習慣化されているので、納得感を持って仕事に向き合えるのがスマレジらしさだと思います。
武:そうしたカルチャーは、入社当時から感じていましたか?
三次さん:はい、当時はまだバリューとして明文化されていませんでしたが、「この会社は目的を大切にしているな」と入社した瞬間から感じていました。実際、「この仕事の目的は何?」といった問いが自然と飛び交っていましたし、私自身も何度も問われました。
一方で、「行けるとこまでいく!」という気合や情熱を感じるバリューもあるんです。論理と情熱のバランスが取れているところも、スマレジらしい魅力のひとつだと思います。
武:ロジカルな視点と気持ちの熱量、どちらも大切にしているのですね。
━━ 社内の雰囲気はいかがですか?
三次さん:落ち着いていて、真摯な雰囲気のある職場です。
スマレジでは、お客様の課題にしっかりと向き合いながら、プロダクトを開発・提案し、導入後も顧客に十分に使いこなしていただくことを目指しています。そのため、着実に積み重ねていくカルチャーが根づいており、誠実に「やるべきことに取り組む」メンバーが多いと感じます。
採用の「もったいない」を減らす、言語化で支えるエージェントの役割

━━ 今まで採用活動をされるなかで、課題に感じている点はありますか?
三次さん:自己応募の方のなかには、転職活動に不慣れで、書類に十分な情報が書かれていないケースもあります。その場合、選考の判断が難しくなることがあります。
面接でも、強みや経験をうまく言語化できず、本来の魅力が伝わらないまま終わってしまう場面もあります。実力があるのに、伝え方次第でチャンスを逃してしまう──そんな「もったいない」と感じることがあるのが実情です。
武: ご自身の強みや経験を、うまく言葉にできず悩んでいる方も少なくない印象です。
菅谷:まさに、私たちエージェントがそこに介在することで価値を発揮したい領域ですね。
三次さん:御社経由でご紹介いただく求職者の方々については、私たちが拾いきれない部分を丁寧に整理し、情報として提供いただけるのがありがたいです。「この方の強みはここです」としっかり言語化されたうえでご紹介いただけるので、選考側としても非常に安心感があります。
━━ 以前、武から求職者をスマレジにご紹介した際の印象についてお聞かせください。
三次さん:推薦時点でご本人の強みや思考が丁寧に整理されていたので、選考に入る前から信頼感がありました。さらに、面接にはしっかりと事前準備をしたうえで臨んでいただき、当社の理解度も高かったため、有意義な時間を過ごせたと感じています。
武:転職のご相談に来られる方の多くは、先ほど三次さんのお話にもあったように、まさに「店舗運営中の店長さん」のような状態に近いと思っています。課題を感じていて何かを変えたいと思っているものの、次に何をすればいいのかが分からない。私たちは、そんな状態の方々に対して、「なぜ転職をしたいのか」「本当に叶えたいことは何か」といった点を一緒に整理しながら言語化します。
そのうえで、希望するキャリアを実現するためのプロセスを描いていく。すると現状がクリアになり、次のアクションが見えてくるんです。
そうして、ご本人が描いた未来像を実現できる企業としてスマレジをご紹介しました。まさに、転職理由や理想像、入社後に目指したいことが自然と一本の線でつながっていったように感じます。
━━ 求職者が自分の考えを言語化できるよう、どんな支援をされていますか?
武:面接の前には、求職者の方と時間をとって壁打ちを行っています。目指しているキャリアや、転職を通じて実現したいことを、どう言語化するか――その表現を一緒に考える時間です。
菅谷:そうした支援があることで、三次さんが「もったいない」と感じるようなケースを減らせるかもしれませんね。
三次さん:まさにそうですね。
菅谷:私たちも普段から言語化をサポートすることを意識していますが、三次さんからのお話を伺い、改めて「言語化できるパートナー」として企業の皆様にお力添えできる部分があると実感しました。
採用成功を導く、エージェントとの対等なパートナー体制

━━ 三次さんがエージェントに望むことを教えてください。
三次さん:要望ばかりお伝えしてよいのか迷う部分もありますが、今の採用市場では企業側のニーズに対して、候補者が不足していると感じています。だからこそ、エージェントの皆さんとはフラットな関係で、共に採用活動を進めていけたらと思っています。
また、営業職の求人倍率など自分でも調べますが、実感とズレを感じることもあります。内向きになりがちな情報に偏らないためにも、採用市況に関する最新の情報を共有いただけるとありがたいです。
菅谷:SaaS業界のリアルな声や市況感は、これからも積極的にお届けしていきたいですね。
武:求職者の生の声も日々集まっているので、そうした情報も引き続きタイムリーにご共有していきます。
━━ SQiL Career Agentに対して、今後どのようなことを期待されていますか?
三次さん:採用ニーズは時期や組織フェーズによって大きく変わります。当社も営業職の採用数が月ごとに変動しているため、そうした変化にリアルタイムで対応できる情報連携を期待しています。
また、SQiL Career Agentさんの強みである「言語化の力」にも期待しています。候補者の情報を単なる経歴だけでなく、その人らしさが伝わる形で整理していただけると、企業としても非常に選考しやすくなります。
武:本日のお話を通しても、三次さんから多くの新しい気づきをいただきました。今後も定期的に情報交換させていただけると嬉しいです。
菅谷:スピード感のある環境を目指す求職者にとっては、最新かつ正確な情報を持つエージェントとの出会いがとても大切です。私たちも「言語化」の支援を通じて、価値のあるマッチングを実現していきたいですね。
武:最適なマッチングのためには、企業とエージェント双方が相互理解を深めることが不可欠です。引き続き、継続的なお付き合いをよろしくお願いします!