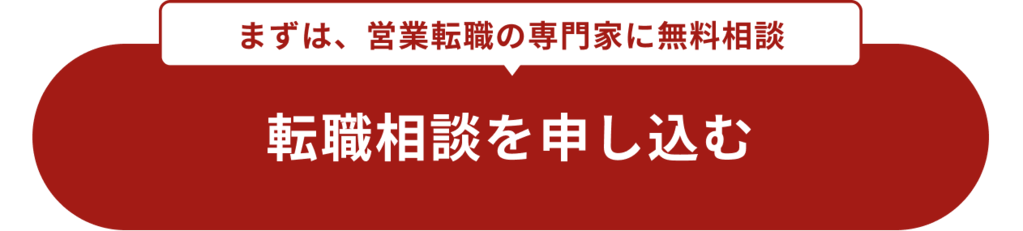人材紹介の営業に向いてる人の特徴とは?|仕事内容・必要スキル・適性を徹底解説
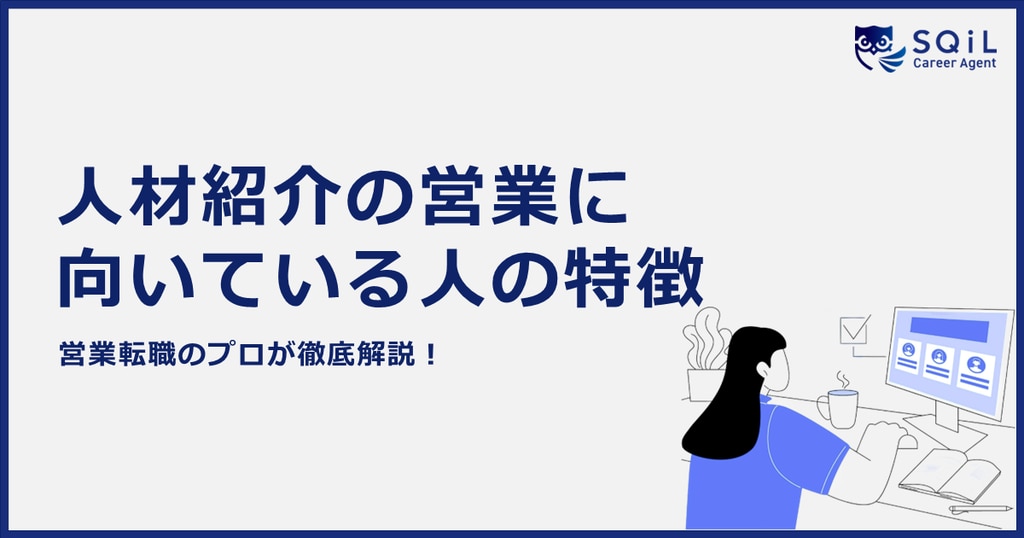
人材紹介の営業は、やりがいが感じられる職種ではありますが、向いている人とそうでない人がいます。特に人の役に立ちたいと考えている人のなかには、この仕事に就きたいと思っている人もいるでしょう。
しかしその一方で「自分が人材紹介の営業に向いているかわからない」「人材紹介の営業はどのような仕事をするのか」といった不安・疑問を抱いている人も少なくありません。
本記事では、人材紹介の営業に向いている人を中心に解説します。仕事内容・向いている人の特徴・キャリアパスなども含めて紹介するので、さまざまな疑問・不安は解消されるでしょう。ぜひ最後まで読んで、人材紹介の営業にチャレンジしてください。
目次[非表示]
- 1.人材紹介の営業とはどんな仕事?
- 1.1.人材紹介業界の構造
- 1.2.法人営業との共通点と違い
- 1.3.担当業務の流れ
- 2.人材紹介の営業に向いている人の特徴
- 2.1.顧客(企業/個人)双方に寄り添えるバランス感覚がある
- 2.2.ヒアリング力や傾聴力が高い
- 2.3.「人の意思決定」にやりがいを感じる
- 2.4.複数タスクの同時進行が得意
- 2.5.短期目標より中長期の信頼関係構築に魅力を感じる
- 3.向いていない人の特徴とは?
- 4.法人営業・SaaS営業経験者は人材紹介に向いている?
- 4.1.共通するスキルと違い
- 4.2.転職時にアピールできるポイント
- 5.人材紹介営業のキャリアパス・年収イメージ
- 5.1.営業職としてのスキルの広がり
- 5.2.年収レンジ・インセンティブの仕組み
- 6.よくある質問(FAQ)
- 6.1.Q. 人材紹介の営業ってノルマがきついの?
- 6.2.Q. 営業ノルマがない人材紹介会社もある?
- 6.3.Q. 企業対応と求職者対応の両方をこなせるか不安です…
- 6.4.Q. キャリアアドバイザー(CA)とリクルーティングアドバイザー(RA)って兼務?
- 7.自分が向いているか不安な人へ|キャリア相談を活用しよう
人材紹介の営業とはどんな仕事?

人材紹介の営業は、企業と求職者の間に立ち、採用を成功に導く仕事です。まずは「どんな働き方・役割なのか」を理解するために、構造や仕事内容を詳しく解説します。
人材紹介業界の構造
人材紹介業界の営業職は、企業と求職者を結びつけて成立した際に企業側から成果報酬を受け取る「成功報酬型」のビジネスモデルが主流です。この仕組みを効率的にかつスムーズに進めるために、RAとCAに分けて業務を担当します。
RA(企業担当) |
CA(求職者担当) |
|
正式名称 |
リクルーティングアドバイザー |
キャリアアドバイザー |
主な役割 |
企業の採用支援 |
求職者の転職支援 |
主な仕事内容 |
|
|
営業体制はRAとCAの両方を別の人が独立して担当する分業型と、一人で兼務する両面型の2種類です。どちらの体制を採用しているかは、人材紹介会社の規模や方針などに左右されます。
法人営業との共通点と違い
人材紹介営業と法人営業は、どちらも「企業の課題をヒアリングし、提案する」点では共通していますが、大きな違いもあります。
観点 |
人材紹介営業 |
法人営業 |
商材 |
「人」という無形商材 |
製品やサービス |
関係者 |
企業と求職者 |
企業側のみ |
成果のタイミング |
求職者が入社して初めて報酬が発生 |
契約成立時に売上が発生 |
特に「BtoB、BtoCの両側面があり、ステークホルダーが2者にわたる」点が、人材紹介営業ならではの難しさでもあり、やりがいでもあります。
担当業務の流れ
担当業務の流れを、RA(企業対応)とCA(求職者対応)の両方の観点から紹介します。RA(企業対応)の担当業務フローは、以下の通りです。
フロー |
内容 |
新規開拓および求人獲得 |
|
採用ニーズのヒアリング |
企業の事業内容や求める人物像などをヒアリング |
求人票の作成 |
ヒアリングした内容をもとに求人票を作成 |
CAへの求人共有 |
作成した求人票をCAに共有して求職者への紹介を依頼 |
選考中の進捗管理・企業へのフィードバック |
|
CA(求職者対応)は、以下のような業務フローが一般的でしょう。
フロー |
内容 |
求職者との面談 |
転職を希望する求職者の経験などをヒアリング |
求人案件の提案 |
求職者の希望・スキルにマッチする求人を複数提案 |
応募書類の添削・推薦 |
|
面接対策・選考フォロー |
|
内定後の条件交渉など |
内定後は給与・入社日などの条件交渉 |
企業と求職者双方の満足度を高めるためにも、RAとCAは連携して業務を進めなければなりません。
💡実際に人材紹介の営業を経験した方の記事はこちら
経験者が徹底解説 - 人材紹介営業のリアル
人材紹介の営業に向いている人の特徴

人材紹介の営業に向いている人の特徴を紹介します。
顧客(企業/個人)双方に寄り添えるバランス感覚がある
人材紹介の営業は企業と個人の両方にアプローチすることから、双方に寄り添えるバランス感覚が不可欠です。
企業に対しては、単に人材を紹介・提案するだけでは充分とはいえません。企業が抱える課題・問題の解決や事業成長につながる提案も必要です。
一方で求職者には、キャリアプランや人生の目標に寄り添った選択肢を提示することが求められます。求職者にとって、新たな就職先が決定して終わりではないからです。
双方の異なる利害を理解しつつ、公平な立場と視点で最適なマッチングを追求できる人は向いているといえるでしょう。
ヒアリング力や傾聴力が高い
人材紹介の営業では、高いヒアリング力や傾聴力も欠かせません。企業・求職者双方の話を聞くことから、業務がスタートするからです。
企業に対しては、特に以下のようなポイントに注目して背景を深く掘り下げる必要があります。
- 事業が抱える課題や問題点
- 人材を必要としているポジションとその理由
- 企業がイメージする具体的な人物像
これらのニーズを正確に把握しなければ、最適な人材紹介はできません。
また求職者に対しては、将来の展望やキャリアの価値観などを丁寧にヒアリングして把握することが重要です。希望条件だけではなく、深掘りしてヒアリングすることで満足度の高い転職サポートができます。
「人の意思決定」にやりがいを感じる
人材紹介営業の仕事は、企業や求職者の「意思決定」に深く関わる仕事です。そのため、自らが主役になるのではなく、相手の選択を支えることにやりがいを感じられる人は向いているといえるでしょう。
企業にとっては「誰を採用するか」、求職者にとっては「どこで働くか」という重要な選択が求められます。どちらも、当事者の未来を左右する大きな決断です。その決断を後押しする存在であることが、人材紹介営業の役割です。
営業が行う提案やアドバイスは、あくまで選択肢を広げるための手段であり、最終的な判断は企業・求職者それぞれに委ねられています。どのような選択がなされたとしても、その決断に納得できるよう伴走し、背中を押すことが大切です。
「自分の介在によって、誰かの未来が前に進む」──そんな瞬間に喜びを感じられる人は、人材紹介営業の仕事に強いやりがいを感じるはずです。
複数タスクの同時進行が得意
人材紹介の営業職では、複数のタスクを同時にこなさなければなりません。その際に求められるのが、マルチタスク能力です。
企業側の場合、複数の求人案件や進捗管理とともに新規開拓も進める必要があります。一方で求職者側では、複数人の面談・面接対策などを同時に進めなければなりません。
RAとCAが分業型の場合はどちらか一方に限られますが、両面型の場合は並行して進めなければならない業務が増加します。複数のタスクを同時進行させたことで混乱してしまい、ダブルブッキングといったミスが起こらないとも限りません。
そのようなトラブルを未然に回避する意味でも、マルチタスク能力が求められるのです。複数タスクの同時進行が得意な人は、混乱することなく優先順位を決めて業務を進められるでしょう。
短期目標より中長期の信頼関係構築に魅力を感じる
人材紹介の営業は、目先の数字にとらわれていては務まりません。中長期的な信頼関係を構築することが重要です。
企業の場合、採用が上手くいかないというケースは珍しくありません。その際には結果を真摯に受け止めるとともに、継続的なパートナーとして継続的に支援し続けることで、次の人材ニーズでも「また相談したい」と思ってもらえる関係が築かれます。
求職者についても転職を成功させて終わりではなく、入社後のサポートも継続的に丁寧かつ親身なキャリア支援をすることで、次の転職の際にも相談してもらえるでしょう。
このように人材紹介の営業は、中長期なつながりを大切にする意識が求められます。長い時間をかけて信頼関係を築くことに魅力を感じる人は、人材紹介の営業がおすすめです。
向いていない人の特徴とは?

人材紹介の営業に向いていない人の特徴も、確認していきましょう。
人との関係構築より数字志向が強い
人材紹介の営業では、目先の数字を追うだけでは成果につながりません。企業や求職者との信頼関係が最も重要だからです。
数字を優先するあまり、ミスマッチな紹介を繰り返してしまうと、企業・求職者の双方からの信頼を失ってしまいます。結果として、エージェントとしての評価も下がってしまうでしょう。
「成果よりも相手としっかり向き合う」姿勢が持てない人には、不向きな仕事といえます。
業務が分業・フロー化されている方が得意
人材紹介の営業は、定型業務よりも臨機応変な対応が求められる仕事です。
人材紹介の営業では、企業と求職者両方の状況をリアルタイムで把握しながら臨機応変に対応しなければなりません。マニュアル通りに進められるケースはほとんどありません。
またタスクも一つずつ進めるのではなく、複数の案件を同時進行させる必要があります。それぞれの状況に応じて最適な対応を判断するためには、柔軟性が不可欠です。
流動的な状況下で仕事を進めることが求められることから、分業・フロー化されている体制が得意な人にとっては、ストレスを感じる可能性が高いでしょう。
短期間で成果が出ないとモチベーションが続かない
短期間で成果が出ないとモチベーションが続かない人も、人材紹介の営業には向いていません。この仕事は、長期的な営業活動が不可欠だからです。
1つの成果に結びつけるためには、以下のようなプロセスを必要とします。
- 企業との関係構築
- 求人獲得
- 求職者の面談・提案
- 書類選考・面接
- 入社決定
上記のなかでも企業との関係構築には特に時間がかかり、入社まで数カ月を要するケースも珍しくありません。
短期間で目に見える成果が得られない状況をもどかしく感じる人は、モチベーションの維持が難しくなってしまいます。
💡キャリアアドバイザーの仕事についてもっと詳しく知りたい方はこちら
キャリアアドバイザーの仕事はきつい?業務内容や向いている人、キャリアパスまで徹底解説!
法人営業・SaaS営業経験者は人材紹介に向いている?

法人営業・SaaS営業経験者は、人材紹介に向いている点を、スキル・アピールポイントに注目して確認していきましょう。
共通するスキルと違い
法人営業・SaaS営業経験者は、人材紹介の営業に向いています。その理由は、共通するスキルが多いからです。具体的な共通点として、以下のようなものがあげられます。
共通スキル |
内容 |
課題解決力 |
顧客の課題を深掘りし、最適な提案につなげる力 |
無形商材の提案力 |
サービス型商材のメリットを可視化して伝える力 |
ヒアリング力・傾聴力 |
ニーズを引き出すためのベーススキル |
信頼関係構築力 |
長期的なリレーションを築く力 |
ただし以下のような違いもあるため、注意しなければなりません。
相違点 |
概要 |
商材の複雑さ・感情要素 |
「人」を扱うため、感情や価値観による変動が大きい |
ステークホルダーの多さ |
人材紹介では企業と求職者の両方が顧客 |
プロセスの不確実性 |
成果が「入社完了」で確定する後払い型のため、 |
スキル面では多数の共通点がありますが、「人」という特有の難しさがある点は考慮しておいたほうがよいでしょう。
転職時にアピールできるポイント
転職時のアピールポイントは、主に以下の通りです。
- 組織課題の深掘り経験:成果が「入社完了」で確定する後払い型ビジネスモデルのため、短期的なクロージングではなく、企業の組織課題を丁寧に深掘りしながら中長期的な提案活動を行った経験を伝える。
- リテンション視点(関係維持力):入社後も求職者・企業と継続的に連絡を取り、信頼関係を構築・維持した姿勢をアピール。転職後の活躍や定着にも関与してきた点を実例とともに伝えると効果的。
- 仮説思考力:市場分析や業界トレンドを踏まえた提案事例を紹介し、クライアントや求職者の課題を言語化し、適切な打ち手を導いた経験を具体的に伝える。
上記のようなスキル・経験に着目してアピールすることで、人材紹介営業職への就職率・転職率が向上するでしょう。
人材紹介営業のキャリアパス・年収イメージ

人材紹介営業のキャリアパス・年収イメージを解説します。
営業職としてのスキルの広がり
人材紹介の営業経験は営業スキルだけではなく、人や組織に関する深い知見や業界知識の習得が可能です。そのため、幅広いキャリアパスを描くことができます。
例えば企業の人材課題を深く理解する力は、事業会社の組織人事やHRBPへの転職が可能です。また、複数の企業を支援する採用コンサルタントへの転身にも直結します。
さらにIT・医療といった特定の業界に特化していれば、その業界の知見を活かした法人営業や事業開発へのキャリアチェンジも不可能ではありません。
マネジメント経験を積めば、営業マネージャーとしてチームを率いる道も開けます。
このように人と組織を深く理解する力やさまざまな業界知識は、多くのキャリアで汎用的に活かせる強みとなるでしょう。
年収レンジ・インセンティブの仕組み
人材紹介の年収は、成果報酬型のインセンティブ制度を導入している企業が多く、成果が年収に直結します。年収レンジは、企業の規模や個人の成果によって変動します。400万円の場合もあれば、1,000万円以上の人もいるので一概にはいえません。
インセンティブの仕組みは、個人で紹介した人材の年収に応じて支給されるスタイルが基本です。例えば年収600万円の人材を紹介したとしましょう。手数料が年収の35%とした場合、インセンティブとしてその一部が支払われます。
外資系・成果主義の企業では、インセンティブが年収の半分以上を占めるケースも少なくありません。高い成果を出せば年収が上がるため、努力がダイレクトに収入に反映される点は魅力といえるでしょう。
しかし、成果が上がらない場合は年収も伸び悩みます。この点は、インセンティブのデメリットといえるかもしれません。
よくある質問(FAQ)
人材紹介営業のよくある質問とその回答を紹介します。
Q. 人材紹介の営業ってノルマがきついの?
人材紹介の営業のノルマに対して、きついと感じている人は少なくありませんが、内容を理解すれば不安は軽減されます。
多くの人材紹介会社では、月間・四半期ごとに売上目標が設定されています。売上目標は、紹介した人材の年収をベースにした成功報酬で計算されることが一般的です。そのため、アポを取ったり面談をするだけでは達成できません。
人材紹介の営業では「入社決定」をもって売上が立つため、目標はアポ数や面談数ではなく、「決定件数」や「売上金額」で設定されるのが一般的です。入社までのリードタイムが長く、タイミングのコントロールも難しいため、結果がすぐに出にくいのは事実です。
ただし、プロセスの質を丁寧に積み上げることで、着実に成果につながる仕事でもあります。目先の数字だけでなく、求職者や企業との信頼関係の蓄積が成果に直結する点にやりがいを感じる方も多いです。
Q. 営業ノルマがない人材紹介会社もある?
完全にノルマがない会社は少数ですが、個人ノルマが緩やかだったり、チーム目標を重視する会社は存在します。とくに日系の中小エージェントや特化型エージェントにその傾向が見られます。
ただし、人材紹介営業も営業職である以上、何らかの「目標」は基本的に設定されています。「完全非営業職」ではないことを理解したうえで、自分に合った働き方ができる会社を選ぶことが大切です。
Q. 企業対応と求職者対応の両方をこなせるか不安です…
両面型(企業・求職者の両方を担当)の場合、慣れるまでは大変に感じることもありますが、一気通貫で対応できることでマッチング精度が上がり、介在価値を実感しやすくなります。
一方で、片面(RAまたはCAのどちらか)を担当できる会社や、入社直後は片面からスタートし、後に両面に挑戦できる体制をとっている会社もあります。不安が強い場合は、企業選びの段階で体制を確認しておくと安心です。
Q. キャリアアドバイザー(CA)とリクルーティングアドバイザー(RA)って兼務?
キャリアアドバイザー(CA)とリクルーティングアドバイザー(RA)を兼務するかどうかは、人材紹介会社によって異なります。
会社が両面型を採用している場合、CAとRAの両方を担当することになります。企業と求職者の双方のニーズを把握しやすく、マッチング精度の高い支援ができる点は大きなメリットです。その一方で、業務範囲が広く、企業対応・求職者対応・日程調整・進捗管理などをすべて担うため、マルチタスク力や優先順位づけが求められます。
一方で分業型の場合は、CAとRAがそれぞれ専門領域に特化して業務を担います。企業対応だけ、あるいは求職者対応だけに集中できる分、専門性を磨きやすいというメリットがあります。ただし、分業になることで担当する件数や対応数が増えることもあり、業務量が少なくなるわけではありません。
どちらのスタイルでも、求められるスキルや忙しさの質は異なるものの、「楽かどうか」という単純な比較はできないという点は理解しておくとよいでしょう。自分の志向や得意なスタイルに応じて、合う環境を選ぶのがポイントです。
自分が向いているか不安な人へ|キャリア相談を活用しよう
人材紹介の営業について解説しました。
人材紹介の営業は、多くの企業・求職者の未来を決定づけるサポートをする仕事です。そのため、やりがい・達成感などが感じられる仕事といえるでしょう。しかし取り扱う商材が感情を持った「人」であることから、誰もが向いているわけではありません。
本記事で紹介した向いている人・向いていない人・キャリアパスなどを参考にして、人材紹介の営業にチャレンジしてみてください。
💡SQiL Career Agent事業オーナー武の人材紹介への想いはこちらの記事から
人材紹介において人が介在する意味とは?「営業職」特化だから実現できる求職者の可能性を広げたいという想い